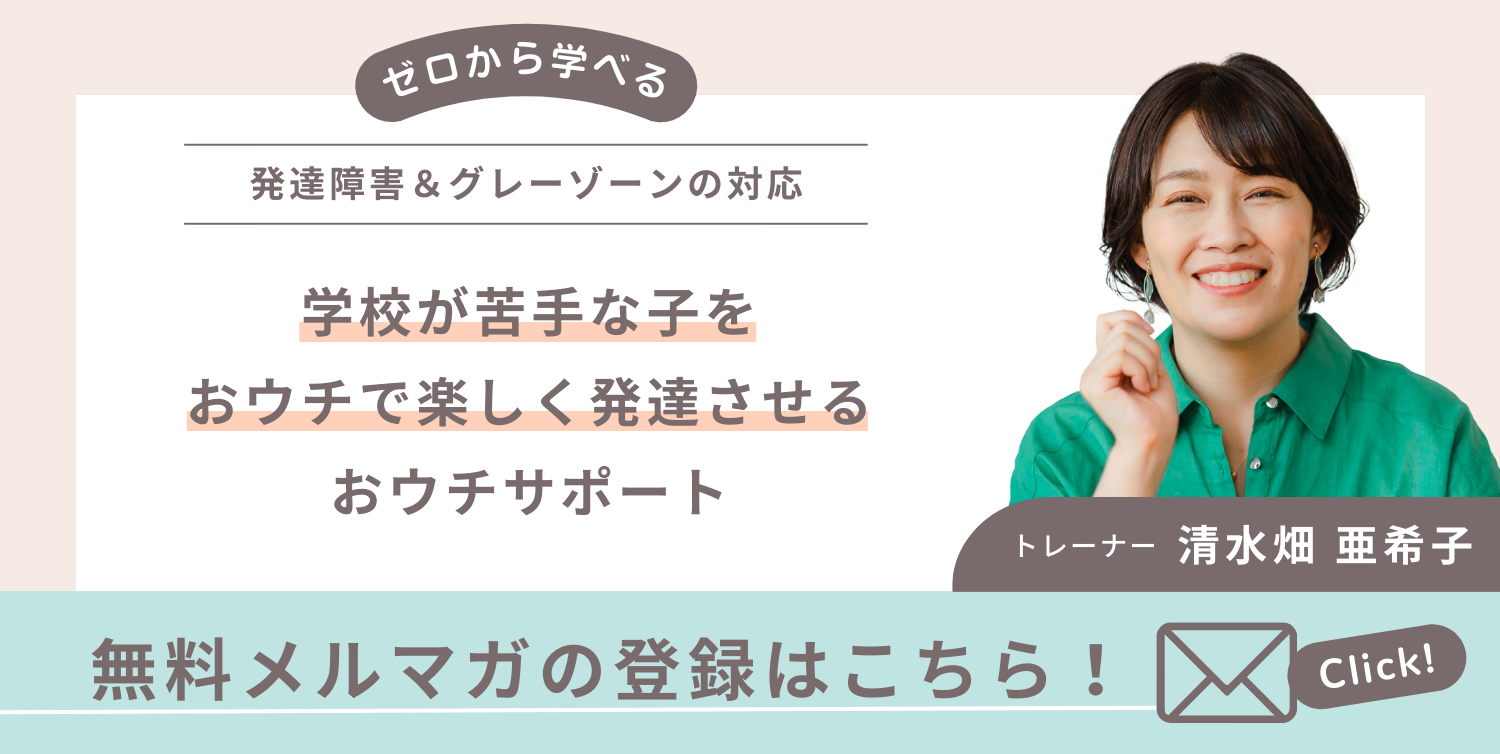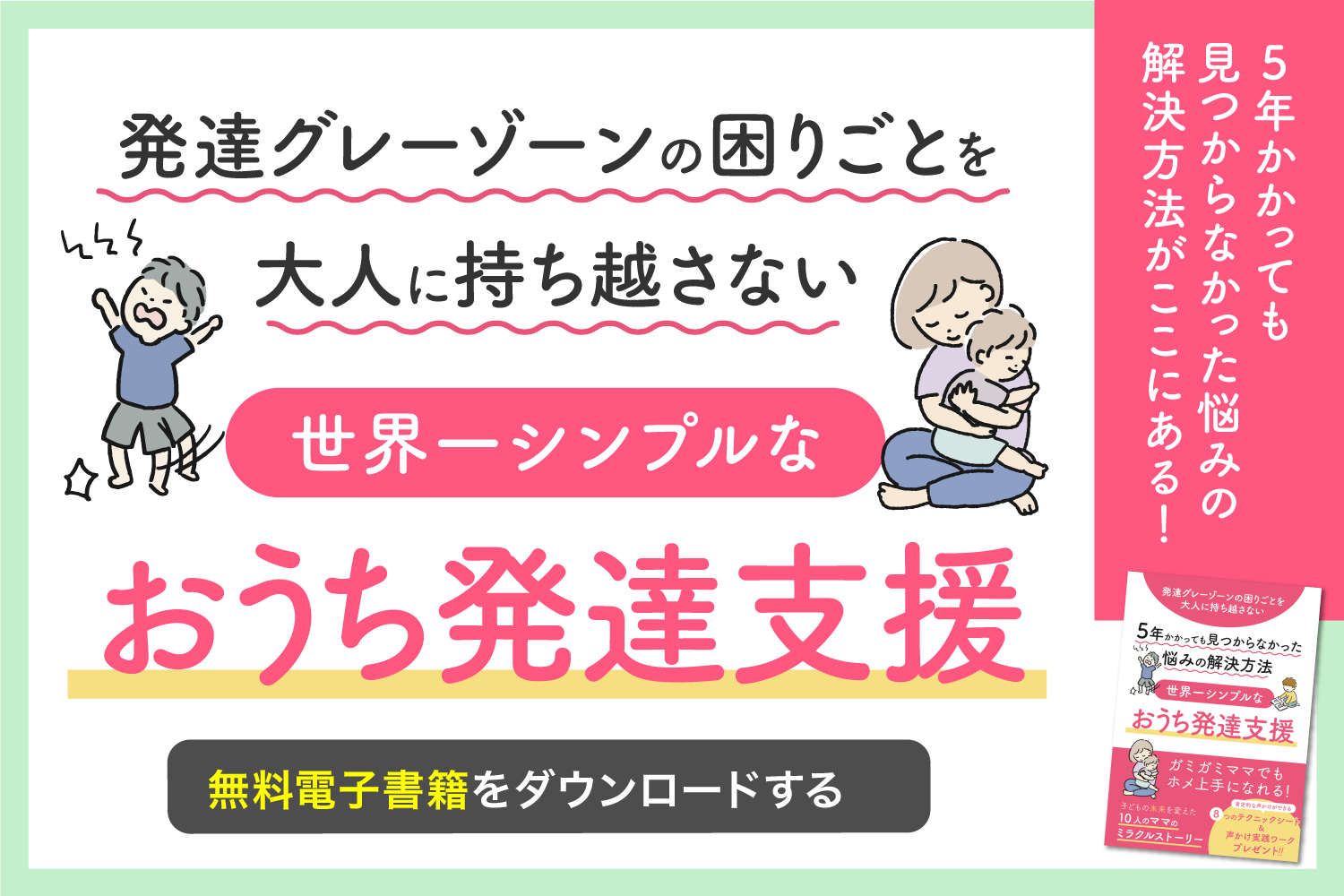小学校入学と同時に一定数の親子が小学校の壁にぶち当たり、母親の生き方を迷走させてしまいます。母親は我慢を強いられ自分のやりたいことは二の次になってしまいます。本当にそれでいいのでしょうか?ママのやりたいを叶える人生を手に入れてみませんか?
【目次】
1.子育てと仕事の両立に立ちはだかる様々な壁
世間では、母親が子育てと仕事の両立を考えたとき、どんなご家庭でも大なり小なり壁が立ちはだかります。
よく耳にするのが子どもが小学校に入ると仕事と子育ての両立が大変になることで言われる 「小1の壁」。
小学校に上がって子どもを預ける先が学童保育になるため、預かり時間が保育園よりも短くなり働き方に制限が出てきたりして起こる壁のことです。
またお子さんが発達障害やグレーゾーンの場合、小学校に入るタイミングで、また別の壁にぶつかります。
落ち着きがないADHD(注意欠陥多動性障害)タイプの子であれば、集団生活や授業のルールにそって動けずにトラブルメーカーとして扱われてしまい、子どもが学校にうまく馴染めずに問題になります。
友達づきあいが苦手なASD(自閉症スペクトラム)タイプの子であれば、友達の意向と違うことをしてしまったり、自己中心的に行動してしまうことでトラブルになることがあります。
そのため社会性を身につけようと放課後デイの検討を考えたりするお母さんもいるのではないでしょうか?
また不安の強いタイプの子であるならば、環境の変化に馴染めず、学校に行けなくなったりすることもあります。
子どもの不安を見過ごしたまま小学校生活に突入してしまうと、先々で母子分離不安症となり不登校になってしまうというケースもあります。
それまでは気に留めていなかったことが困りごととして表面化してくるのも、ちょうど小学校低学年の時期。本当にこの時期は学校への対応や放課後の対応などから、母親が仕事と子育ての両立に悩んでしまいます。

発達障害・母子分離不安・不登校のお子さんがいるお母さんの声を聞いていると、
・お迎えがあるので母親は17時までしか働けない
・子どものことを理解してくれる職場が見つからない
・そのため、復職ができないまま時間がたってしまった
という声が聞かれます。ここから見えてくるのは「働きたくても、働けない母親」という実態です。
金銭的にも余裕が欲しいという理由や、自分にやりがいのあるものを見つけたい!と小学校進学のタイミングで仕事を始めようと思っていても仕事をするためには、職場の理解や配慮がないと難しいのが現実なのです。
また、障害の程度が重ければそもそも仕事をしようという発想にもならないと思います。
でも、そんな立場にあるお母さんにこそ「働く」ということを大切にして欲しいし、諦めて欲しくない!と思っています。
そして、母親として胸を張って生きてもらいたい!心からそう思います。
母親の新しい働き方をぜひ考えてみませんか?
2.発達障害・分離不安・不登校の子をもつ母親が仕事をするには制限がつきもの
実は、子どもの小学校進学の時期に働き方に悩む母親は3人に1人です。そして、実際に退職や転職を決意する母親が4人に1人いると言われています。
これは一般的な調査なので、発達障害・母子分離不安・不登校の子どもを持つ家庭だけでアンケートをとったら、退職や転職をする母親の割合はもっと多いかもしれません。
では、どうして発達障害の子どもがいると仕事をするのが大変になるのでしょうか?
一般的に、発達障害がある子の主な進路としては
・普通級に在籍する
・普通級に在籍しながら、週1~2回の通級指導を受ける
・特別支援学級に在籍する
・特別支援学校に通う
という選択肢があります。
もしも普通級に進学した場合、放課後は学童や放課後デイサービスで過ごすことになります。
ただ、放課後デイは空きがなく入れない場合もありますし、学童の場合は発達障害があると延長の利用は不可という場合もあります。
そうなると、17時以降は民間保育サービスを利用する必要が出てくるかもしれません。
特別支援学級に進学する場合は、自宅から学校までが遠いと集団登校の班にも入れず、朝の送りが必須になります。
さらに放課後は、送迎付きの放課後デイが見つからないと、小学校から放課後デイの施設まで送ってくれるサポートも探す必要が出てきます。
一般的に考えても発達障害がある子どもの場合は様々な制約があり、さらに高い壁を超えなければならないということです。
また発達障害がある子どもだけに限らず、母子分離不安・不登校の子どもの場合、

・療育に連れて行く日は仕事を休まなければいけない
・クリニックや相談センターなど、複数の相談先に行くために何度も休みが必要になる
・いつ学校に行きたくないと言い出すかわからない
・トラブルがあると、急に学校から呼び出される
など、たくさんの悩みがあって仕事を再開できない、そんな状況のお母さんが多いのではないでしょうか?
そんな難しい子育てにチャレンジしているお母さんたちは、どうしても自信を失いがちです。
その自信のなさが不安につながり、不安によって起こるイライラに苦しむことも多いのではないでしょうか?実は、私自身がまさにそんな状態でした。
ただでさえ子どもがいると学校行事で休みを取ることが多いのに、子どもが小さい頃は病気もしたので看病や通院でも休みを取とりました。
さらに学校トラブルの対応で休みをとったりしたので、1年で40日も休みをもらった年もありました。
そんな状態での仕事は大変でしたし、いつ学校から飛び出されるかとビクビクしながら仕事をして、いつも周りに申し訳ないと思いながら働いていました。
でも今は、時間や場所を選ばない柔軟な働き方ができるようになったので、そういった周囲への気遣いの大変さからは解放されています。
私をそんな風に変えてくれた、発達科学コミュニケーションを活かした働き方についてお伝えさせてください。
3.あなたの子育て経験を活かせる仕事があります!
私が所属する発達科学コミュニケーションのラボには、発達科学コミュニケーションを教えるトレーナーという仕事と、裏方としてリサーチの仕事などをして記事にするリサーチャーという仕事があります。
どちらの仕事も在宅でできるので、お子さんの予定に合わせて働くことができます。
そのおかげで私は、息子が行きしぶりを悪化させて家で過ごすことが多くなったときにも、息子のペースに合わせて過ごすことができました。
「仕事があるから子どもには学校に行ってほしい」なんて無理強いをする必要がなくなりましたし、子どもの様子を毎日観察することができたんです。
そのときほど「いつでも」「どこでも」パソコンひとつでできる仕事をしていて本当によかった!と感じたことはありませんでした。
しかも、子どもの発達のことをしっかり学びながら仕事にしていくことができたのが本当に良かったです。
発達科学コミュニケーションのラボで活躍しているのは、子どもの発達やご自身の子育てについて悩んでいた「元・どん底時代経験組」のお母さん達ばかり!
・暴言を吐いたり、キックやパンチをしてくる思春期男子
・自信のなさから心因性の症状が出て、学校に行けなかった小学校男子
・常にかんしゃくを起こして大絶叫していた幼児さん
・気持ちをうまく表現できず、殻に閉じこもっていた繊細な思春期女子
そんな子どもたちと向き合いながら、ご自身の仕事を調整してきたお母さんたちばかりです。
それが今では、発達のことを学び、我が子の発達については誰よりもわかっているプロになり、仕事も子どものことも頑張る決意をされています。

今の日本社会では、発達障害の子どもを持つお母さんが仕事を続けようと思うと、その子育て環境がマイナスに捉えられることが多いです。
ところが、発達科学コミュニケーションでは、「つらかった子育てを、自分の力で解決してきた」その経験全てが「強み」に変わっていくんです!
「困った行動」に注目せず、「いい力」を伸ばすにはどうしたらいいのか?
いつもそんな視点で子どもの行動を観察して、発達のことを学んだ母親としての経験そのものが武器になる「すごくお得なお仕事」なのです!
今とても大変な思いをしているお母さん達も、目の前の子育ての悩みを解決することがゆくゆくのお仕事に繋がっていく可能性もあるんです。
そう考えると、もう下を向いて生きていかなくてもいいと思いませんか?ご自分の経験と可能性に自信を持ってくださいね!
コロナウイルスの影響で、今では在宅ワーク・テレワークが一般的になりました。
時間や場所に縛られない働き方は、子どもの予定との調整もしやすいので発達凸凹のあるお子さんがいるお母さんにピッタリの働き方ではないでしょうか?
しかも、発達科学コミュニケーションのラボでの仕事は自分の子育ての経験が活かせます。
お子さんに発達障害があるからといって、それを負い目に感じる必要なんてありません!そんな新しい働き方に興味のある方は、先ずは無料のメルマガに登録することから始めてみてくださいね。
執筆者:清水畑亜希子
(発達科学コミュニケーショントレーナー)
(発達科学コミュニケーショントレーナー)