発達障害のお子さんが学校に1人で行けず、付き添い登校に疲れた!とお困りのことありませんか?母子登校を卒業するコツは不安を解消し、安心できる環境づくりをすることです。付き添い登校しながらできる環境づくりをお伝えします。
【目次】
1.発達障害の子が小学校に1人で行けない
2.付き添い登校とは
3.付き添い登校に疲れたらどうする?
4.母子登校を卒業する発達障害の子の環境作り
①子どもの不安の原因をさぐる
②安心できる友達づくりをお手伝いする
③安心できる支援をお願いをする
2.付き添い登校とは
3.付き添い登校に疲れたらどうする?
4.母子登校を卒業する発達障害の子の環境作り
①子どもの不安の原因をさぐる
②安心できる友達づくりをお手伝いする
③安心できる支援をお願いをする
1.発達障害の子が小学校に1人で行けない
発達障害の小学生のお子さんの登校しぶりがひどく、1人で小学校に行けない、母子登校が続いているとお困りのことありませんか?
発達障害の子どもが1人で小学校に行けないときは、実は学校生活に大きな「不安」を感じている場合があるんです!
そのため、登校しぶりや母子登校を卒業するコツは、子どもの不安を解消することにあるんです。
我が家の子どもも登校しぶりが激しく、1人で小学校に行くことができなかったとき、仕事を休んで付き添い登校(母子登校)をしたことがありました。
その時の経験をもとに、付き添い登校しながら母子登校卒業に向けて子どもの不安を解消する環境調整をすることができたので、こちらの記事ではその方法をお伝えしていきます。
では、発達障害の1人で小学校に行けない子どもはどのような不安を抱えているのかご紹介します。
・感覚過敏のつらさで疲れた
・授業で発表のときに間違えて、恥ずかしい思いをした
・友達が怒っていても、理由がわからない
・活動の見通しがつかない
小学校に行くとまたうまくいかないかもしれない…と、失敗経験から不安になってしまうこともあります。
さらに、周りからは想像しづらい理由で不安になっていることもあります。
例えば、発達の偏りがある子どもは、自分と他人の境界線が乏しいと言われています。自分が怒られていなくても、他の子が怒られていることを自分のことのように感じて、小学校に行けなくなる子もいます。
また、誰にでもあるような失敗を非常に大きなことと捉えて、「自分はもうダメだ」と思い込む子もいます。
先生にあてられたときに答えられなかったことを非常に大きくとらえて、授業の参加に恐怖を感じて学校にいけなくなることもあります。
このように小学校でたくさんの感情が押し寄せてくることや、感覚過敏でたくさんの刺激を浴びて疲れたりすることがあるのです。

そんな子どもの特性からくる不安の強さや極端な受け取り方を「自分の育て方が悪かったの?」とお母さんが自分を責める必要はありません。
発達障害の子どもはネガティブな記憶を強化しやすい傾向があります。不安が出やすい遺伝子の存在も認められており、生まれつきの体質として、不安になりやすい傾向をもつ子どももいるのです。
2.付き添い登校とは
付き添い登校とは、学校に行くことに不安がある子どもと保護者が一緒に登校することをいいます。
1人では行けないけれど、安心できるお母さんと一緒なら学校に行けるし、学校にいられるという子もいます。

母子登校とも言いますが、小学生だと、このような対応があります。
・登下校のみ親が付き添い、クラス前まで一緒に行く
・学校の授業中に別室で、親が付き添う
・授業中もクラスの中で、親が同席する
母子登校にも様々な形がありますし、学校での許可が必要なこともあります。
発達グレーゾーンの困り事を
大人に持ち越さない
親子のコミュニケーションがわかります
↓↓↓
大人に持ち越さない
親子のコミュニケーションがわかります
↓↓↓
3.付き添い登校に疲れたらどうする?
付き添い登校(母子登校)をすると、お母さん自身も体力的にも精神的にも疲れたり、限界を感じることありませんか?
他の子と自分の子の違いが見えて、辛くなったり、いつまで母子登校が続くの?と不安を感じることもありますよね。
疲れを解消するためには、母子登校の卒業の見通しを持つことが大切です。
どういうことかというと、付き添い登校を頑張っているご自分を労いながら、付き添い登校しながら、子どもの不安を解消するヒント探しや環境調整をしていくのです。
学校に出入りできることをチャンス!ととらえて、母子登校卒業に向けて、情報収集と関係づくりの場として活用していきましょう。できることはたくさんあります!

4.母子登校を卒業する発達障害の子の環境作り
発達障害の子どもの母子登校を卒業するためには、小学校の中に安心できる存在や環境を増やしていくことが大切です。
安心できる先生、支援員さん、友達を増やす、疲れたと感じさせないよう安心して受けることのできる授業を増やしていくのです。
不安にさせる授業は、見学や、保健室など別室で受けられるようお願いします。遅刻、早退しながら、子どもが大丈夫といった授業から参加していきます。
そして、子どもが大丈夫と言ったところから付き添いも外していきます。
では、具体的に、母子登校卒業に向けて、付き添い登校しながらお母さんにできることをお伝えします。
◆①子どもの不安の原因をさぐる
まずは付き添い登校のときは、お子さんの不安の原因を知る機会にしていきましょう。
原因がわかることで、不安を解消する対策を立てていくことができます。
お子さんの学校での授業の様子を見て、何に不安を感じているか、どんなことに疲れたと感じるか、観察して推測していきます。
例えば、先生がクラスメイトを叱ったことが原因で先生が怖くなって学校にいけない…このような子どもの独特な受け取り方が原因だと、なかなか不安の原因が判明しづらいこともあります。
また、本人が不安の原因に気づけていなかったり、説明できないこともあります。
そのため、お母さんが授業の様子を見て、子どもが何を不安と思っているか情報収集します。
◆②安心できる友達づくりをお手伝いする
安心できる友達との関係づくりが、子どもが1人で学校に行けるきっかけになることがあります。
そのため自分の子どもを気にかけてくれる親切な子には、積極的にコミュニケーションを取って、感謝を伝えて、いい関係をつくるようにします。
「準備手伝ってくれてありがとう。」
「授業の始まりに声掛けてくれてありがとう。チャイムに気付かないことがあるから、助かってるよ」
安心できる友達が登校を促す場合もあります。普段仲良くしている友達に迎えに来てもらうことで、登校できるようになった子もいました。

◆③安心できる支援をお願いする
クラスをサポートする支援員さんと会う機会もあるでしょう。
あまり直接相談する機会がない方ですが、困り感のある子を直接的にサポートしてくれる方です。立ち話で支援員さんにこんなサポートをしてほしいと、お話しできる機会もあるでしょう。
私は付き添いしているときに、小学校の支援の体制で、通級とは別に個別で学習しているケースがあることに気付きました。
学校独自の支援として、取り出しで個別学習をしていました。枠が少ないため、公表していない支援でした。
当時息子は集団での学習がつらくなっていた時期。希望して、個別学習の支援をつけてもらうことができました。
付き添い登校をしていたおかげで、このような独自の支援に気づくこともでき、子どもが安心して学習を受ける環境づくりをすることができました。
登校しぶりのピンチをチャンスととらえて、小学校に出入りできることをしっかり活用してみましょう。
支援のお願いができたり、子どもが不安に思っていることを解決する糸口がみえて、1人で行けるようになっていきます。
今回は付き添い登校(母子登校)でできることをご紹介しました。
お母さんも疲れたり辛い状況ですが、大丈夫です!ピンチをチャンスに変えながら、子どもの安心を一緒に広げていきましょう。
お子さんが「学校に行きたくない!」というときは、ぜひこちらもチェックしてみてくださいね。
安心して月曜日をむかえられる方法をご紹介しています▼▼
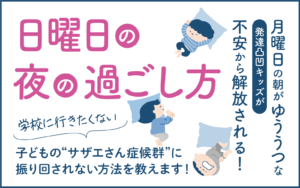
月曜日の朝がゆううつな発達凸凹キッズが不安から解放される!日曜日の夜の過ごし方
執筆者:森富ゆか
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)
(発達科学コミュニケーションリサーチャー)





