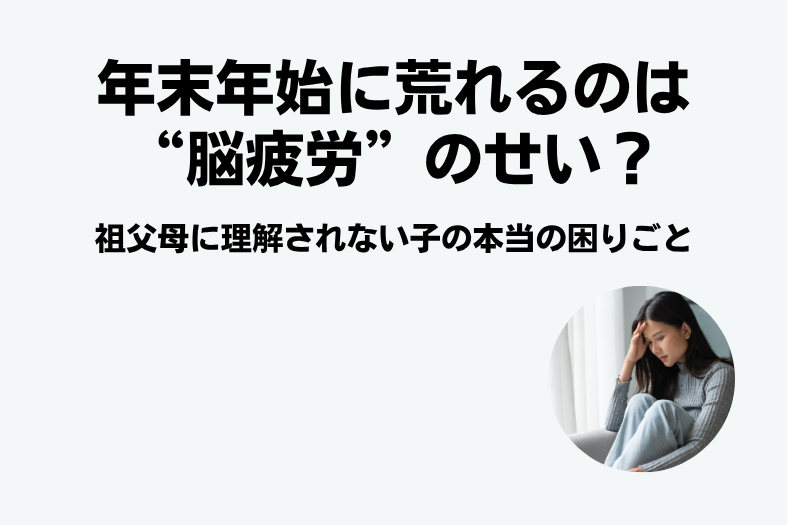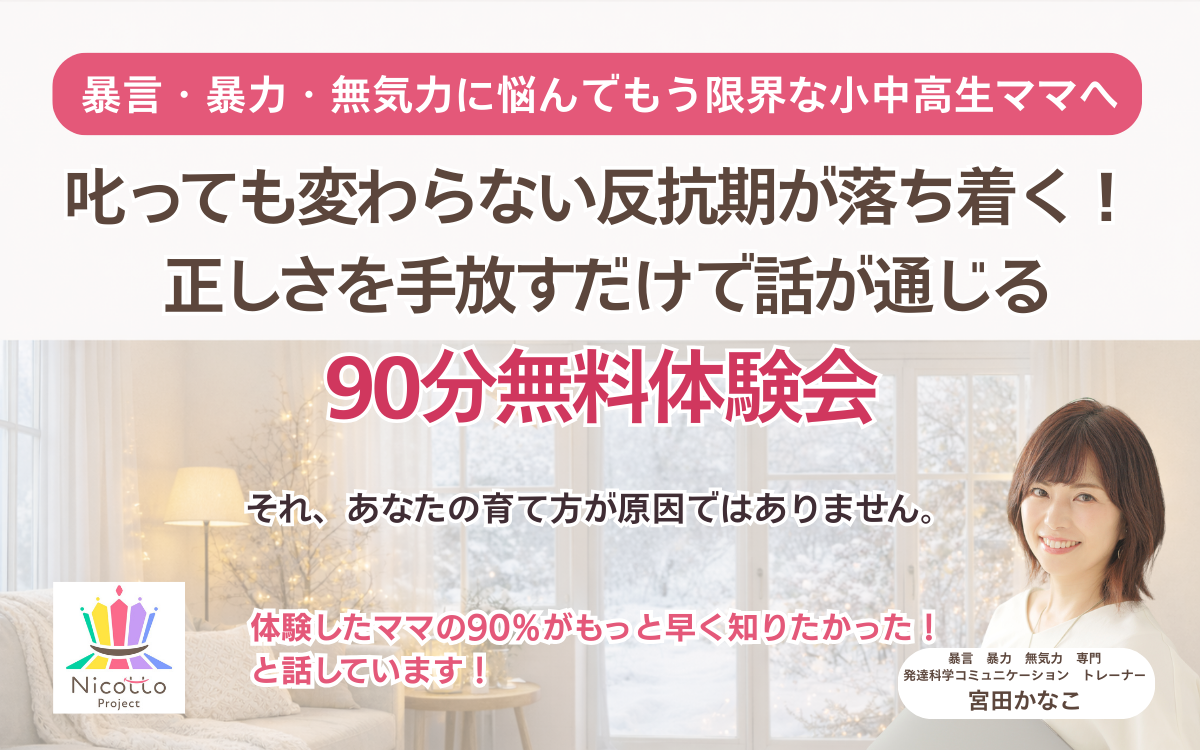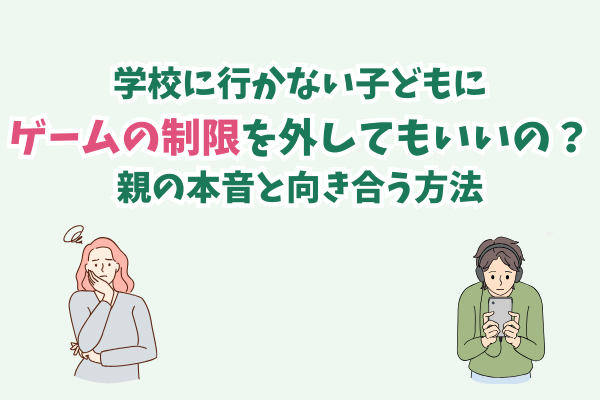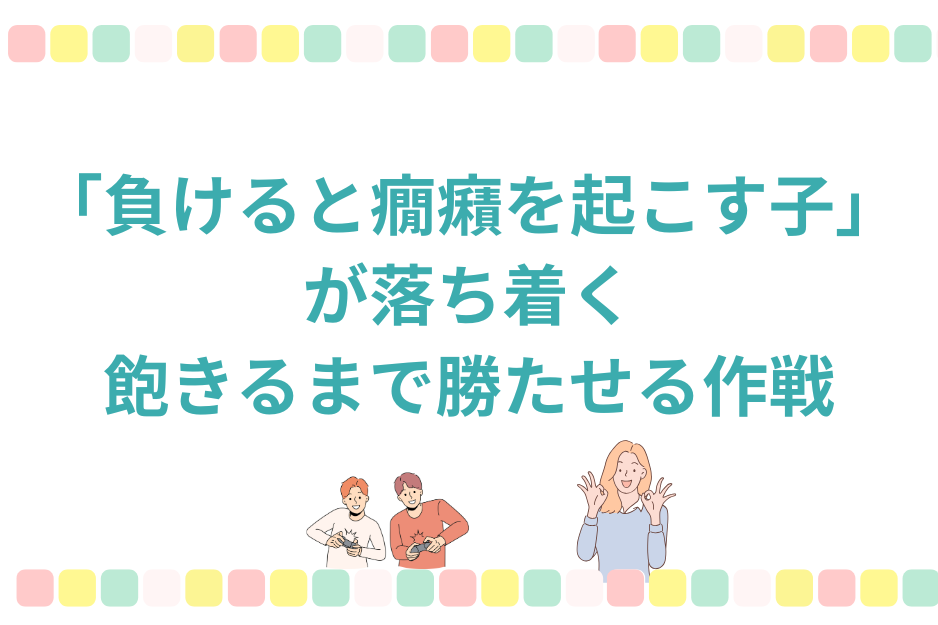年末年始になると、子どもがイライラしたり、暴言が増えたり、急に不機嫌が続く…そんなことはありませんか?
実はこの時期、表面の“行動”よりも脳の疲れが溜まりやすい季節特有の要因 が大きく関係しているんです。
今日は、祖父母や親戚にも理解されにくい子どもの“本当の困りごと”と、冬休みにできるお家のケアをお伝えします。
年末年始に「荒れやすい」3つの理由
生活リズムが崩れる
冬休みは普段のように登校がなく、
・起床時間
・スマホやゲーム時間
・夜の過ごし方
が乱れやすくなります。
そして冬は気温差が大きいため、体温調整に“脳のエネルギー”を多く使います。
つまり、生活リズムの乱れ × 冬の体調負担=脳がすぐに疲れる
この状態が積み重なると「不機嫌」「暴言」「脱力」「無気力」といった“困った行動”として表に出てきます。
祖父母・親戚からの“理解されない圧”
年末年始に増えるのが、親戚・祖父母からの無意識のひと言。
「そんな甘やかすからよ」
「もっと叱らないと」
「昔はこんな子いなかった」
これらは“正しさ”からの言葉。
しかし発達特性のある子には正しさは刺激が強すぎて脳疲労が悪化します。
子どもは「どうせ分かってもらえない」と感じ、ママは「また私が責められる…」と苦しくなる。
誰も悪くないのにすれ違いだけが積み重なってしまうのです。
親や周囲が「この子は困っているんだ」と見方を変えるだけで、子どもは守られていると感じ、少しずつ落ち着きはじめます。
冬休みは“刺激の変化”が多すぎる
・帰省・イベント・環境の変化・人の多さ・音や匂い・予定の詰め込み…
普段より刺激が強く、脳が情報過多になりやすい時期です。
発達凹凸の子は刺激の処理がまだ未発達なため、どうしても疲れやすくなります。
脳が疲れたサインは次の3つです。
・すぐ怒る(戦う)
・ぼーっとする(固まる)
・布団から出られない(逃げる)
どれも “悪い行動”ではなく、SOSの表現 です。
親ができる冬休みの3つのケア
①「落ち着ける場所」を確保する
帰省先・旅行先では子どもが安心できるスペースが減ります。
・いつも遊んでいる物を持たせる
・イヤホンを持たせて音刺激を減らす
・行事は全部参加しなくてOK
“安心の逃げ場”を作ると、荒れにくくなります。
② スケジュールを詰めすぎない
予定を詰めるほど、脳のキャパを超えます。
・一日に予定は1つまで
・人に合わせすぎない
・「今日は休む日」と宣言して良い
「休む勇気」は子どもにも伝わります。
そして、その安心が伝わることで、子ども自身も落ち着いていく。
③ 祖父母には「簡単に伝える」のが一番ラク
長く説明する必要はありません。たった一言で十分です。
「この子は人より脳が疲れやすいタイプで、刺激が多いとしんどくなります。」
責めるでもなく、説得するでもなく、“情報として伝えておく”。
それだけで理解者が1人増え、ママの負担は大きく減ります。
ママが“理解者”になれたら、子どもは必ず落ち着く
実は、子どもにとって冬休みでいちばん大事なのはママが安心しているかどうか。
ママが「一緒にいられる」「守ってもらえる」と脳が安全だと感じるからです。
すぐに行動を直さなくていい。すぐに頑張らせなくていい。
あなたが“最初の理解者”になるだけで、冬休みの親子関係は驚くほど穏やかになります。
この冬、関係を整えたいお母さんへ
冬休みと年末年始は「荒れやすい季節」ですが、実は 親子関係が変わる大チャンス でもあります。
もしあなたが、
・暴言・不機嫌が続いてしんどい
・帰省が憂うつ
・祖父母に責められるのが怖い
・冬休みが地獄になるのではと思っている
そんな状態なら、一度立ち止まって整えるタイミングです。
今のまま我慢し続けなくても大丈夫。
この冬を“関係が動き出す季節”にしませんか?
必要な方は体験会の案内を読んでみてくださいね。
2026年こそ、親子関係を変える第一歩を。
無料体験会実施中!
「うちでも変われる?」
「どう関わればいいの?」
「こんな悩み、私だけ?」
そんな不安がある方は、
ぜひ体験会にいらしてください。
どんなママも初めは不安です。
だけど、同じ悩みを抱えた仲間がいると
その瞬間から心がすっと軽くなります。
暴言・暴力・無気力な子どもが動き出す
“脳を育てる関わり方”を、
あなたのご家庭でも体感してみませんか
▼画像をクリックして詳細を見る