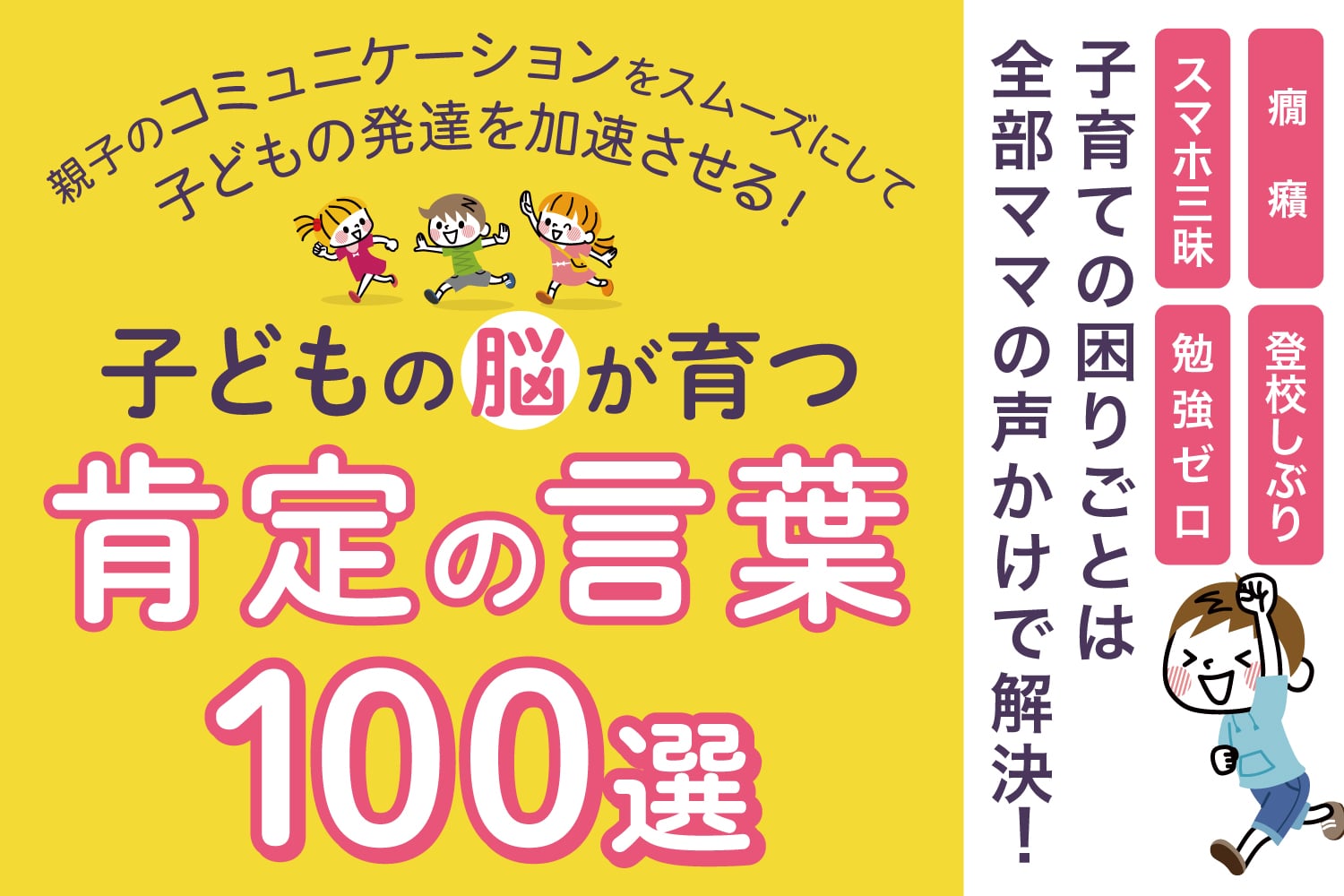友達トラブルが絶えない小学生。「協調性がない=発達障害?」と悩む前に知ってほしい原因と家庭でできる対応をまとめました。今日からできる声かけと見守りで、お子さんの強みが伸びる関わり方を紹介します。
【目次】
1.なぜ「協調性がない=障害?」と不安になるのか?
2.協調性が苦手でも大丈夫?小学生の個性を伸ばす視点
3.協調性が苦手な子にぴったり!見守る子育ての理由
4.協調性が苦手でも才能に変えられる!今日からできる具体策
1.なぜ「協調性がない=障害?」と不安になるのか?
学校では「みんなと同じであること」が強く求められます。そのため、親は「うちの子だけ違う」と不安になりやすいのです。
ですが、実社会に出れば、流されずに意見を言えることってすごく大切な力なんです。
子どもが小学生になると、友達トラブルや学級での指摘が増えて、
「うちの子、協調性がないのかな?」
「もしかして障害?」
と心配になるママはとても多いです。
しかし、協調性がないように見えても、実は成長の途中で自然に伸びる力だったり、将来の強みの種だったりすることも多いです。
実際、私の息子も「協調性がない」と学校で見られやすかったのです。
打ち上げの誘いを断ったり、掃除中に友達と話して注意されたり、家では暴言もあり、私は不安でいっぱいでした。
息子は自分のペースや価値観を大事にして、同じ趣味や目的を持つ友達とは心から楽しんで遊んでいました。
打ち上げに行かない選択も、自分で決めたからこそ満足感があったようです。
この記事では、なぜ協調性のなさが「障害?」と不安につながるのか、協調性がないことは本当に問題なのか ?
友達トラブルの裏にある本当の理由と見守ることで子どもが変わる理由と今日からできるママの対応をまとめました。
ママの不安が少しでも軽くなるように、子どもの才能を伸ばす具体的な関わり方について最後にお伝えしますね!

▼▼1日スマホばかりの中・高校生にお困りのママへ▼▼
手が付けられない癇癪は
私のせい?と悩むママへ
私のせい?と悩むママへ
指示出しゼロの子育てで
たった3週間で癇癪が着く!
↓↓
▼無料ダウンロードはこちらから▼
2.協調性が苦手でも大丈夫?小学生の個性を伸ばす視点
「協調性がない=即トラブル」ではなく、 「まだ伸びる途中の個性」 として捉えましょう。なぜなら、協調性がないことは マイナスではなく、強みに変えられる可能性 があるからです。
しかし、子ども同士のトラブルが起きると、つい「協調性がないから?」「発達障害なのかな…?」と心配になってしまいますよね。
実際に多くの小学生を見ていると、友達トラブルの裏には “性格” や “発達特性” だけでは説明できない、いくつもの背景が重なっていることがあります。
大切なのは、「怒って止めるべき行動」なのか、それとも「成長の途中として見守るべき行動」なのかを、見極める視点を持つこと。
そのためには、表面の「ケンカした」「仲間に入れない」「空気が読めない」という行動だけではなく、本当の原因を知ることが、ママの心を軽くし、子どもの成長を支える第一歩になります。
●子ども本人が困っていないなら、大きな問題ではない
友達と全く関われないわけじゃなくて、好きなことや目的が合えば一緒に遊べる。これは社会性がゼロではなく、「選んで関わっている」ということ。
友達と全く関われないわけじゃなくて、好きなことや目的が合えば一緒に遊べる。これは社会性がゼロではなく、「選んで関わっている」ということ。
●“協調性がない”は“自分の意見を持てる”の裏返し
人に流されずに自分の考えを貫けるのは、将来社会で役立つ強み。研究者・起業家・アーティストなども、むしろ周りに合わせすぎない個性から生まれている。
人に流されずに自分の考えを貫けるのは、将来社会で役立つ強み。研究者・起業家・アーティストなども、むしろ周りに合わせすぎない個性から生まれている。
●年齢と経験で自然に伸びていく力
子どものうちは「自分が中心」で当然。大人になっていく過程で、必要に応じて協調性は育つ。焦らなくても、安心して見守ることで伸びていく。
子どものうちは「自分が中心」で当然。大人になっていく過程で、必要に応じて協調性は育つ。焦らなくても、安心して見守ることで伸びていく。

今できていないからって心配しなくて大丈夫。見守ることで、子どもは自分のタイミングで協調性も育ちますよ。
3.協調性が苦手な子にぴったり!見守る子育ての理由
「見守る=放任」ではなく、子どもの主体性を尊重しながら支えるスタイルだからこそ、協調性が苦手な子に合うんです。
● 強制されると反発しやすいから
協調性が低い子は「みんなと一緒にやろう」という指示や圧力にストレスを感じやすいです。無理に従わせようとすると「やりたくない!」と反発して、余計に孤立することも。
→ 見守ることで 本人のペースを尊重できる。
●自分で選ぶ経験が自己効力感につながる
「遊びに行く・行かない」「クラブ活動に参加する・しない」など、小さな選択を積み重ねることが、「自分で決められた」という自信につながります。
→ 協調性よりもまず 自立心を育てることができる。
● 受け入れられている安心感が、協調性を育てる土台になる
「みんなに合わせられない自分」を否定されず、親に見守られていることで、「ここなら安心して自分でいられる」と感じられる。
→ その安心感がやがて他者への思いやりや協調性を生む。
見守ることで、わが子も自分で考え、行動する力を少しずつ身につけていきました。
怒るのは、“人を傷つけたり、危険があるときだけ”で大丈夫。
それ以外は、ちょっと待って見守りながら、子どもの「違い」を伸ばす時間です。
例えば、友達と遊ぶ順番でもめちゃうときも、すぐ口を出さずに見守ってみる。
そうすると、子どもは自分で折り合いをつける力を少しずつ身につけていきます。
授業中に発言できずに悩んでいても、少し見守るだけで、自分なりの参加の仕方を見つけられることもあります。
家でのお手伝いや片づけも、無理に促さずに見守ることで、自分のペースで取り組む習慣が育ちます。
友達に意地悪されて泣いたときも、すぐに助け舟を出さずに少し待ってみる。
子どもは、自分で気持ちを整理したり、どう対応するか考える力を育てられるんです。
子どもは、安心できる環境の中でこそ、協調性も社会性も、ゆっくりでも確実に育っていきます。
そしてその成長は、ママが「ちょっと待ってみよう」と勇気を出した瞬間から始まります。

具体策は最後にお伝えしますね!
▼▼朝起きられない子どもにはこちらの記事を参考にしてくださいね▼▼
▼ADHD中学生が部活辞めたいときの対応はこちらの記事をどうぞ▼
毎日の声かけで“脳のクセ”は変えられる!
子どもが持つ力を発揮できるようになる
4ステップの声かけ
↓↓↓

無料ダウンロードはこちらから
↓↓
https://www.agentmail.jp/lp/r/21301/169708/
4.協調性が苦手でも才能に変えられる!今日からできる具体策
ママが今日からできる子どもの才能を伸ばす一歩としてできることは何でしょうか?
●焦らず見守る
●選択と自己決定の経験を大切にする
●「欠点ではなく個性」と考える
●少しずつ行動の幅を広げ、社会との関わりを経験させる
強制や叱責で直そうとするのではなく、子どもが自分で選び、行動する機会を増やすことが、協調性のなさを才能に変えるカギです。
私は、「ちゃんとやりなさい」と強制するのではなく、見守ることを選びました。
できていないことはスルーしつつ、提案するだけ。
「打ち上げに好きな食べ物がなくても、友達から面白い話が聞けるかも。」
「学校とは違う友だちの一面を知ることもできるし、楽しい世界があるんだよ」
遊びに行きたいなら行かせる!
お家に遊びにつれてきてもよし!
おこづかいはかかる時もあるけれど、そこから生まれるコミュニケーションや思い出が、自己効力感につながると思ったからです。
高校生になった今、息子は、
・小中学校の友達とはたまに遊ぶ
・高校の友達は校内だけの付き合い
・土日は基本的に自分時間(ジム、キックボクシング、アルバイト)
一見すると「友達と遊ばない子」に見えますが、本人は不服もなく楽しそうです。
目的が同じ友達とは楽しく遊ぶこともあり、コミュニティにはしっかり属しています。

協調性がないことは困りごとに見えるかもしれません。
以前の私は協調性がない息子が友達と遊ぶとトラブルが起きるのではないかとハラハラ!そんなことはよそめに、息子は友達と遊びたがる子でした。
だけど、高校生に成長した息子は、「自分時間を楽しむことができる」才能が見出せました。
そして、 自分の意見を持ち、相手に伝えられる力という強みも手に入れました!
子どもの個性を「欠点」ではなく「才能」として伸ばす視点を持てば、ママも安心して子育てできます。
まだ私も子育て進行形なので、息子の個性を才能として伸ばしていきたいと思います。
焦らず見守り、子どもの成長を一緒に楽しんでいきましょうね!

「協調性がない=障害?」と悩むママの不安を解くために、よくある質問(FAQ)
Q1. 協調性がないのは障害のサインですか?
A:必ずしもそうではありません。多くの場合「まだ成長の途中」や「自分の意見をはっきり持っている」だけのこと。困っているのが子ども本人ではなく、周囲の大人や友達であるケースもあります。
Q2. 協調性がない子は将来、社会で苦労しませんか?
A. 協調性は年齢や経験とともに自然に育ちます。大人になってからも学べる力です。それよりも「自分の考えを持てる」という強みを伸ばすことが、社会での大きな武器になります。
Q3. ママはどう対応すればいいの?
A. 無理に「みんなと同じにしなさい」と言うよりも、子どもの気持ちを尊重しながら見守ることが大切です。「あなたの意見も大事だよ」と伝えることで、子どもは安心して人と関わる力を育てていきます。
▼▼中学生になっても兄弟喧嘩⁉年の差の兄弟喧嘩にお困りのママへ▼▼
▼わが子をどう褒めたらいいのか迷ったらこちらをどうぞ参考にしてくださいね▼